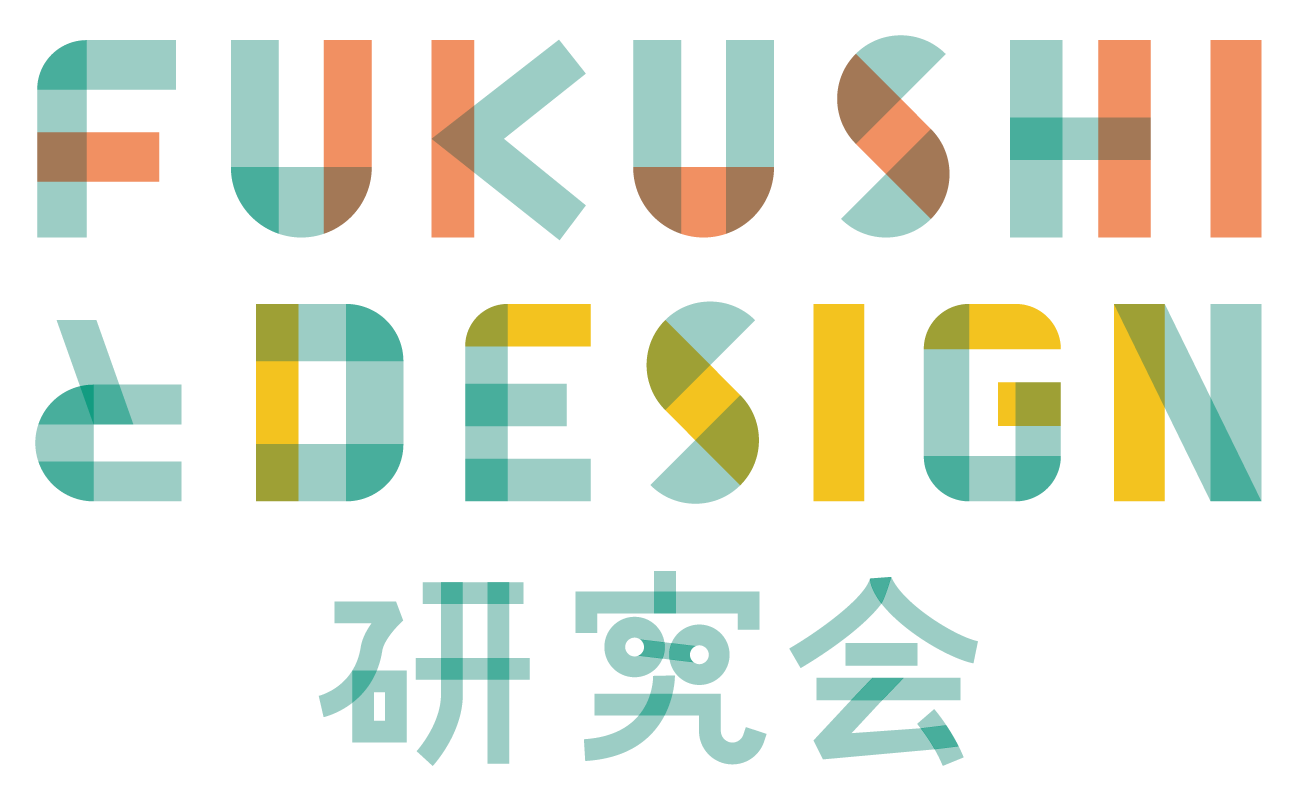インクルーシブデザインと福祉
【実施概要】
日時 2022/9/21(水) 18:30-20:00
場所 長浜カイコー
参加者 約20名
「福祉とデザイン」をテーマにしたセミナーシリーズ、「福祉とデザイン研究会 2022」を開催しています。
第一回は、シブヤフォント アートディレクターのライラ・カセム様をお招きし『「インクルーシブデザインと福祉」グラフィックデザイナーが見る現場でのデザインの活かし方』というテーマでお話頂きました。
福祉分野の最前線でご活躍される方やクリエイター、学生など、様々な方が市内・県内・県外から22名ご参加されました。
ゲストレクチャー ライラ・カセム様
ご自身のバックグラウンドをもとに、インクルーシブデザインに関わり始めたライラさんは、2種類のインクルーシブがあることに気がつきます。一つ目は、「当事者の視点を考案と製作段階に取り入れ共同でデザインを開発する」というやり方。二つ目は、「デザインを必要とする現場の人々と共にその場にあった持続可能な解決策をつくりあげる」というやり方。ライラさんは特に後者に可能性を感じ活動をされています。インクルーシブと対極にある排除。各々が持っている「排除の種類」を検討し、何にアプローチするのかをその場にあった形で検討していくというやり方です。

法規制や世間の流れから叫ばれる社会参加。社会参加とは何か?ということを考え、大学院に戻る中で出会ったのが綾瀬ひまわり園。典型的な福祉施設で、特段アートに特化した活動を行う場所では無かったものグラフィックデザイナーのライラさんから見ると素敵な作品を生むような場所だったそうです。
そこで気づいたことは才能ではなく機会の問題だということ。いわゆる障がい者アートとして才能があるように扱われる作品と綾瀬ひまわり園で生まれる作品の違いは、才能の有無ではなく機会の有無だとライラさんは話します。そしてその機会は、ライラさんのようなデザイナーが介入した後でも持続するものである必要があると指摘します。
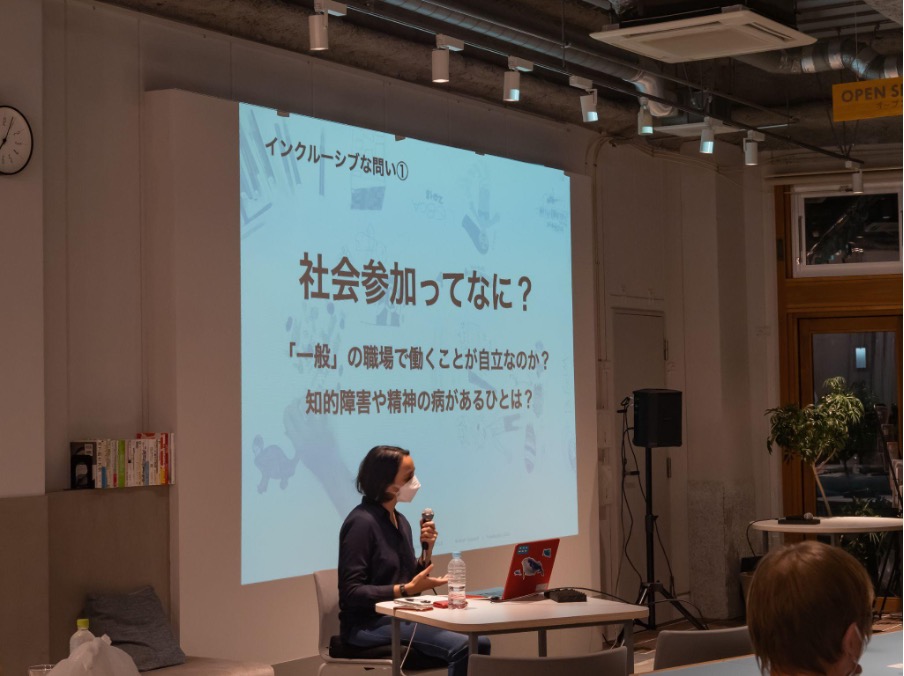
そこでぶつかった問いが「どうやったらみんなが関われるか?」。施設に関わる人の観察を通してアーティスト(利用者)、施設、デザイナーなどそれぞれ何が出来るかをプロット。製品販売を通して事業化させることもひとつの方法とはいえ、生産設備、価格設定や販売、クオリティの維持は難しい。どうすれば、多くの施設を巻き込めるのかというのはライラさんにとっての課題でした。ライラさんが選んだのは、アートのクオリティを上げるということでした。職員の方にアーティストのポテンシャルを理解する観点を与え、またアート活動の重要性に気づいてもらうため「創造能力を開花する8つの方法」を開発されました。素敵な作品が作られるようになり、さらに施設で作られるものをデザインに活かせるかということを考えた時にライラさんが編み出した発想はパターンにするということでした。パターンにすることにより、デザイナーや施設の方が実際に使えるデザインになる。また、そこで生み出されたデザインは自分たちでつくり出すものでも、他者に提供し使ってもらうものでも良い。そして施設にとってもデザインを利用する人にとっても関わりやすいものとするため、イラスト・文字の形態に着目しました。
そんな中、渋谷区をより多くの人に好きになってほしい、シティプライドを感じてほしいという願いのもと生まれたのが、区の障がい福祉課で採択されたシブヤフォント。現在6年目で400以上の柄と50以上のフォントが作られました。今では一般社団法人として渋谷区と共催という形で活動されています。シブヤフォントの特徴としては、創作だけでなく創作からその方の特性が分かり支援が繋がることもあるという創作と支援が両立されるということがあげられます。また、学生との協働のプロジェクトという形を取ることも特徴の一つです。学生が関わることで、デザイナーが施設に入り協働するよりもフラットなお互いの学び合いの場が創出されます。さらに、施設の職員が学生に対して普段の施設での活動を説明することは職員の方の活動への更なる動機付けの場にもなります。アーティストの特性を理解し、信頼関係を構築できるだけの長い期間を通して関わるからこそ学生は、編集など介入する範囲の判断ができるのです。
多様な企業に利用されてきたシブヤフォントですが、現在その活動を広げ、やり方を伝授するフェーズにも入っています。地域の福祉施設とデザインコミュニティーを繋げ、施設を地域の文化拠点にしたいという思いのもと始まったこの活動は、滋賀県の「創作ヴィレッジこるり村」含め全国に広がっています。
よりインクルーシブなデザインを果たすには、多様な人に対し多面的に働くプロセスであるべきだということ。そのためには、ゴールは短期のものと長期のものを設定すること。状況把握とそれぞれのスキルをリストアップすることはその実現のために重要だとライラさんは話します。また、問いはモチベーションに繋がること、目標は実際に今持っているスキルとバランスを持って設定すること、プロセスは一直線でなく、階段のように一つずつ進んでいき、振り返りながら考える必要性を指摘。それに伴い時間が必要な福祉という分野においては、目標設定や評価は、結果により行うのではなくプロセスやインパクトを通して行ってほしいということもお話されました。
グループに分かれてお話
「あなたが思う福祉はなんですか?その中で自分ができることは?」ということをテーマにグループに分かれディスカッションを行いました。福祉をメインフィールドに活動している方だけでなく多様なバックグラウンドを持つ参加者同士が交流することを通じて新たな問いが育まれるような場になりました。
ライラ・カセム氏
障害福祉の現場の創作活動とデザインを繋げ、共同制作を通して商品開発やさまざまなプロジェクト企画・運営。障がいのある人々の経済自立・社会参加とデザイナーや企業の社会意識を促す活動をしている。
その象徴でもある「シブヤフォント」ではアートディレクターを務め、近年で本プロジェクトはグットデザインや内閣府オープンイノベーション対象など多数の賞を受賞。東京大学特任研究員、桑沢デザイン研究所非常勤講師なども務める。
記事執筆/ Takuho Soejima 撮影/Miwako Yamauchi